私は救急病院で約10年間勤務したのち、スポーツ整形外科クリニックに転職し、3年目を迎えようとしています。現在のクリニックでは、一般撮影と骨密度測定を担当しています。
救急病院でも一般撮影は一通り経験していたため、ある程度の自信を持っていました。しかし実際には知らないことも多く、勉強になる事が沢山あります。
今回は、私がスポーツ整形外科クリニックで学んだことのひとつ、「腰椎の立位撮影」についてご紹介します。
あくまで私個人の意見ですが、参考になれば幸いです。
脊椎専門医との会話から学んだこと
ある日、脊椎専門の先生とお話する機会があり、「腰椎の立位撮影」には多くのメリットがあることを教えていただきました。
実際に取り入れてみて感じた、いくつかの利点をご紹介します。
1. 時間短縮が可能
腰痛のある患者さんの多くは、寝たり起きたりする動作が困難です。だから立位で撮影することで、ベッドへの移動や体位変換が不要になり、撮影時間の短縮につながります。
これは私たち技師だけでなく、患者さんにとっても大きなメリットです。
2. 機能性側弯の評価が可能
立位で正面撮影を行うと、機能性側弯を呈する方を多く見かけます。
機能性側弯とは、脊椎そのものが曲がっているのではなく、痛みや姿勢の影響によって一時的に側弯を呈する状態です。
撮影する前に、姿勢不良や体の傾きが目立ち側湾を疑っても、臥位で撮影すると意外と真っ直ぐという経験をしたことも多いです。
逆に立位撮影の時は側湾を認めたけど、骨密度測定の臥位検査時は側湾でない方も多くいます。
だから立位で正面撮影を行う事で、構造的な変化だけでなく、骨盤の傾きや機能性側弯を観察出来る事も多いです。
注意としては、立位撮影でもAP方向で撮影すると、患者さんが背面のパネルに寄りかかることで、臥位と変わらないような画像になることがあります。
だから私は可能な限りPA方向での立位撮影を選択しています。どうしても立位が困難な場合や転倒のリスクがある場合は、座位AP方向で撮影しています。
3. 診断がしやすくなることも
荷重状態(立位または座位)で撮影することで、圧迫骨折など椎体の潰れが観察しやすくなります。
特に側面撮影では、椎体前方の凸変化が観察しやすくなります。
さらに、立位や座位のみで変化が見られない場合でも、臥位での追加撮影(正面・側面)を行うことで、荷重時との比較が可能になります。
これにより、椎体の高さの変化をより正確に評価できます。
また圧迫骨折だけでなく、すべり症や椎間の狭小化も観察しやすくなります。
さらに姿勢や反り腰に関連がある、骨盤傾斜の情報も同時に得らことが出来ます。
4. デメリットと対応策
腰椎立位撮影の唯一のデメリットは、特に高齢者において、体位保持が難しい場合に画像がブレやすいことです。
また転倒のリスクも忘れてはなりません。
そのような場合は、座位撮影や点滴棒など支持するもの持ってもらうなど、安全かつ安定した撮影ができる工夫をしています。
まとめ:撮影方法の選択で得られる情報は変わる
教科書では、腰椎の一般撮影は「臥位」での撮影が基本とされています。私も救急病院時代は、ほとんど臥位で撮影していました。
病院とクリニックでは患者層が異なります。また施設や医師の考え方の違いもあります。だから一概に、立位撮影が良いとも言えないかもしれません。
しかし臥位撮影は構造的変化の評価に適している一方で、一般撮影だけでは異常を捉えきれないこともあります。
特にクリニックでは、すぐにMRIを撮れない場合も多いため、一般撮影でどこまで診断価値のある画像を提供できるかが問われます。
そのような時、立位や座位での荷重撮影を取り入れることで、構造的変化だけでなく、機能的な変化も可視化できる可能性があります。
もちろん限界はありますが、撮影方法を工夫することで得られる情報は増やせると実感しています。
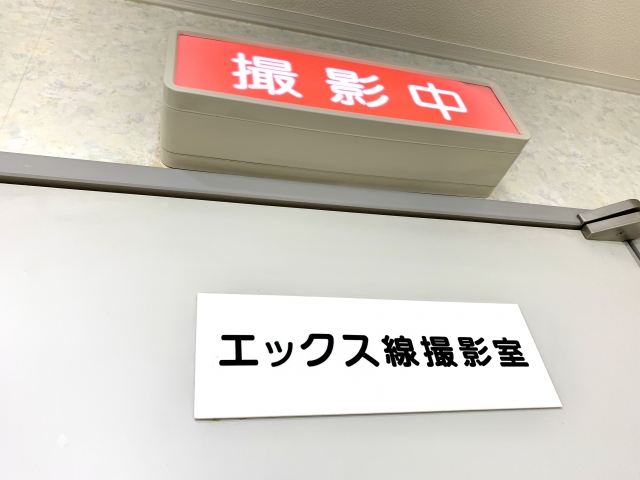


コメント